診療科紹介
消化器・代謝内科は、1977年に大学整備拡充事業の一環として開設され、多くの人材が集まり、専門領域も拡大してまいりました。現在では多数の当科出身の医師が、奈良県を中心とした各地域の病院との密接な連携のもとに、消化器(消化管・肝胆膵)疾患、代謝性疾患を中心とした診療を担当しております。
現在、附属病院において、年間30,000人以上の外来患者さんを診療し、1,000人以上の新しい入院患者さんを関連病院との密接な連携のもとに、奈良県はもとより他府県からも多数受け入れています。また、急性期消化器疾患に対しても奈良県腹部救急ネットワークを介して全例受け入れることを基本的方針としており、緊急内視鏡検査をはじめとした救急患者の診察を行っています。当科の第1の目標は十分な医学的知識・技量と真の「癒しの心」を持って患者さんに信頼される医療を行うことにあります。消化器外科、放射線科など関係科との定期カンファレンスをいくつも行っており、1人1人の患者さんに対する最適な治療を診療科の枠を越えて考えるようにしています。
診療内容
消化器は、消化管(食道、胃、小腸、大腸)と肝臓、胆道、膵臓からなり、癌(がん)が多く発生する領域です。癌は早期に発見することが肝要で、超音波や内視鏡、超音波内視鏡、CT、MRI等を用いて早期診断に努めています。
早期に発見された肝臓癌や食道・胃・大腸癌などは、ラジオ波凝固療法(RFA)や内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)などの超音波や内視鏡を応用した最先端の医療機器を駆使して治療しています。進行癌に対しても、消化器外科、放射線科、腫瘍放射線科などと密に連携して、専門的で集学的な治療を実践しています。
また、ウイルス肝炎や肝硬変、食道・胃静脈瘤、胆石症、膵炎、胃・十二指腸潰瘍や潰瘍性大腸炎・クローン病といった腸疾患などの良性疾患についても、各専門スタッフが、安全でより効果的な最新の医療を提供しています。
代謝分野の代表的な疾患はメタボリック関連疾患で、綿密な病態分析のもと、きめ細かい治療を行っています。
主な対象疾患
C型肝炎
C型肝炎ウイルスに感染することで、慢性肝炎、肝硬変と進行していきます。内服治療にてウイルス排除ができるようになっており、現在では進行した肝硬変でも治療適応が拡大しており、積極的に治療を行っています。
非アルコール性脂肪肝疾患(NAFLD/NASH)
飲酒習慣がなくても、生活習慣病(メタボリックシンドローム)や肥満が原因で脂肪肝になる病気で、肝硬変まで進行することもあります。血液検査、画像検査、肝生検による診断の上、患者様の栄養状態などに基づいた指導を含めた治療を行っています。
肝硬変
肝炎ウイルス、アルコール、脂肪肝などが原因で徐々に肝機能が悪化し、肝硬変に至ります。肝硬変に至ると、黄疸、腹水など症状が出現したり、肝臓がんの発生リスクが高まります。症状に対する治療や肝臓がんの早期発見のための定期的な画像検査を行っています。
急性胆管炎
胆石やがんなどが原因で胆管が閉塞し、胆汁の流れが悪くなった状態を閉塞性黄疸と言います。閉塞性黄疸に細菌感染が加わると急性胆管炎を起こし、内視鏡や経皮穿刺で溜まった胆汁の排出(ドレナージ)を行います。
急性膵炎
アルコールや胆石などが原因で発症します。絶食や点滴で加療し、胆石が原因の場合は内視鏡治療(ERCP)を行うこともあります。膵炎が落ち着いた後に膵嚢胞ができることがあり、超音波内視鏡(EUS)を用いたドレナージを行うこともあります。
食道がん
飲酒や喫煙が食道がん発生のリスクとされています。早期であれば、内視鏡治療にて切除可能です。外科、放射線科、腫瘍内科と連携し、進行度に応じて、外科治療、化学療法や放射線療法を行っています。
胃がん
多くはピロリ菌が原因となって発生します。早期であれば内視鏡治療にて切除可能です。外科、腫瘍内科と連携し、進行度に応じて、外科治療、化学療法を行っています。
大腸がん
大腸ポリープが進行すると大腸がんになります。早期であれば内視鏡治療にて切除可能です。外科、腫瘍内科と連携し、進行度に応じて、外科治療、化学療法を行っています。
肝臓がん
慢性肝炎や肝硬変では肝臓がんができやすいとされており、早期発見のため超音波検査、CT、MRIで画像検査を行います。発見された際は、外科や放射線科と連携し、手術やラジオ波焼灼(RFA)、肝動脈塞栓術(TACE)を行っています。
膵臓がん
膵臓がんが疑われた際は、ERCPやEUS-FNAと呼ばれる内視鏡検査で正確な診断を行います。外科、腫瘍内科、放射線科と連携し、進行度に応じて、外科治療、化学療法、放射線治療を行っています。
お知らせ
2023年6月15日(木)、16日(金)に奈良市で第59回肝臓学会総会が行われ、当科教授 吉治仁志が会長を務めております。
-
教授
吉治 仁志よしじ ひとし
専攻分野 - 消化管・肝・胆・膵 疾患
所属学会 - 日本内科学会
- 日本消化器病学会
- 日本肝臓学会
- 日本消化器内視鏡学会
- 日本癌転移学会
- 日本門脈圧亢進症学会
- 日本高齢消化器病学会
- 日本肝類洞壁細胞研究会
- 日本肝癌研究会
- 日本肝癌分子標的治療研究会
- 急性肝不全研究会
- 肝形態科学研究会
- 酸化ストレス研究会
- 肥満と消化器疾患研究会
- アルコール医学生物学研究会
- 肝と糖尿病・代謝研究会
- 肝不全治療研究会
- サイトプロテクション研究会 他
主な資格・認定 - 日本内科学会認定内科医・総合内科専門医・指導医
- 日本消化器病学会専門医・指導医
- 日本肝臓学会専門医・指導医
- 日本消化器内視鏡学会専門医・指導医
- 日本医師会認定産業医
- 厚生労働省認定人体病理解剖指定医
- 医学博士
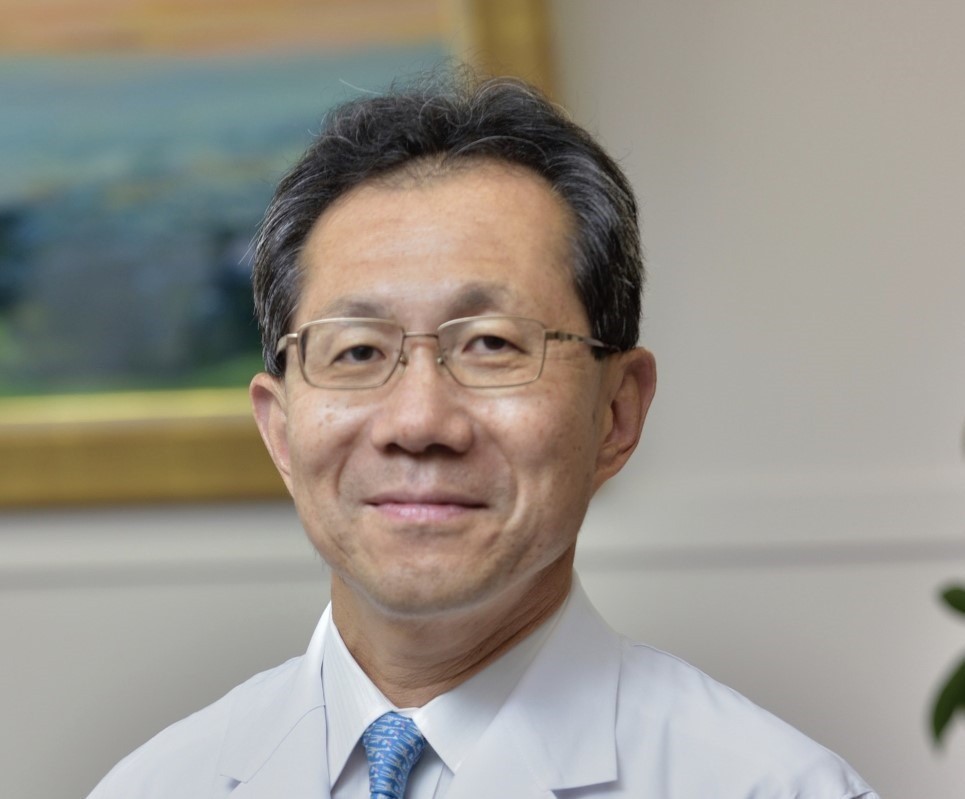
-
病院教授(中央内視鏡部)
美登路 昭みとろ あきら
専攻分野 - 消化管・肝・胆・膵 疾患
所属学会 - 日本内科学会
- 日本消化器病学会
- 日本肝臓学会
- 日本消化器内視鏡学会
- 日本胆道学会
- 日本消化管学会
- 日本膵臓学会 他
主な資格・認定 - 日本内科学会認定内科医
- 総合内科専門医・指導医
- 日本消化器病学会専門医・指導医
- 日本肝臓学会専門医・指導医
- 日本胆道学会指導医
- 日本消化器内視鏡学会専門医・指導医
- 日本消化管学会胃腸科認定医・専門医・指導医
- 日本膵臓学会専門医・指導医
- 日本医師会認定産業医 医学博士
-
講師
浪崎 正なみさき ただし
専攻分野 - 消化管・肝・胆・膵 疾患
所属学会 - 日本内科学会
- 日本消化器病学会
- 日本肝臓学会
- 日本消化器内視鏡学会 他
主な資格・認定 - 日本内科学会認定内科医・総合内科専門医・指導医
- 日本消化器病学会専門医・指導医
- 日本肝臓学会専門医・指導医
- 日本消化器内視鏡学会専門医・指導医
- 日本医師会認定産業医
- 医学博士
-
講師
鍛治 孝祐かじ こうすけ
専攻分野 - 消化管・肝・胆・膵 疾患
所属学会 - 日本内科学会
- 日本消化器病学会
- 日本肝臓学会
- 日本消化器内視鏡学会 他
主な資格・認定 - 日本内科学会認定内科医
- 日本肝臓学会専門医
- 医学博士
-
学内講師
西村 典久にしむら のりひさ
専攻分野 - 消化管・肝・胆・膵 疾患
所属学会 - 日本内科学会
- 日本消化器病学会
- 日本肝臓学会
- 日本消化器内視鏡学会 他
主な資格・認定 - 日本内科学会認定内科医
- 日本肝臓学会専門医
- 医学博士
-
学内講師
北川 洸きたがわ こう
専攻分野 - 消化管・肝・胆・膵 疾患
- 胆道・膵臓疾患の内視鏡診断・治療 (ERCP, EUS-FNA, Interventional EUS)
- 膵胆道系悪性腫瘍の化学療法
所属学会 - 日本内科学会
- 日本消化器病学会
- 日本肝臓学会
- 日本消化器内視鏡学会
- 日本胆道学会
- 日本膵臓学会 他
主な資格・認定 - 日本内科学会認定内科医・総合内科専門医
- 日本消化器内視鏡学会専門医・指導医
- 日本消化器病学会専門医・指導医
- 日本胆道学会指導医
- 日本膵臓学会指導医
- 医学博士
コメント 消化器疾患全般、特に胆道・膵臓疾患の診断・治療に従事しております。
胆道・膵臓領域は、近年内視鏡技術 (ERCP、EUSなど) の進歩が目覚ましい領域です。また、切除不能膵癌・胆道癌に対しても、新規の抗癌剤が開発されております。消化器外科や放射線科、腫瘍内科とも緊密に連携しており、困難例に対しても出来る限り患者様にとってベストな治療を提供出来るように心がけております。
当院での治療を御希望される胆道・膵臓疾患の患者様がいらっしゃいましたら、地域連携室を通じて御相談下さい。 -
助教
藤永 幸久ふじなが ゆきひさ
専攻分野 - 消化管・肝・胆・膵 疾患
所属学会 - 日本内科学会
- 日本消化器病学会
- 日本肝臓学会
- 日本消化器内視鏡学会 他
主な資格・認定 - 日本内科学会認定内科医・総合内科専門医
- 日本消化器病学会専門医・指導医
- 日本消化器内視鏡学会専門医・指導医
- 日本肝臓学会専門医
- 医学博士
-
助教
辻 裕樹つじ ゆうき
専攻分野 - 消化管・肝・胆・膵 疾患
所属学会 - 日本内科学会
- 日本消化器病学会
- 日本肝臓学会
- 日本消化器内視鏡学会
主な資格・認定 - 日本内科学会認定内科医
- 日本消化器病学会専門医・指導医
- 日本消化器内視鏡学会専門医
- 日本肝臓学会専門医
- 医学博士
-
助教
竹田 惣一たけだ そういち
専攻分野 - 消化管・肝・胆・膵 疾患
所属学会 - 日本内科学会
- 日本消化器病学会
- 日本肝臓学会
- 日本消化器内視鏡学会
主な資格・認定 - 日本内科学会認定医
- 日本消化器病学会専門医
- 日本消化器内視鏡学会専門医
- 日本肝臓学会専門医
-
助教
久保 貴裕くぼ たかひろ
専攻分野 - 消化管・肝・胆・膵 疾患
所属学会 - 日本内科学会
- 日本消化器病学会
- 日本肝臓学会
- 日本消化器内視鏡学会
主な資格・認定 - 日本内科学会認定医
- 日本消化器病学会専門医
- 日本肝臓学会専門医
- 日本消化器内視鏡学会専門医
-
診療助教
友岡 文優ともおか ふみまさ
専攻分野 - 消化管・肝・胆・膵 疾患
所属学会 - 日本内科学会
- 日本消化器病学会
- 日本肝臓学会
- 日本消化器内視鏡学会
主な資格・認定 - 日本内科学会認定医
- 日本消化器病学会専門医
- 日本肝臓学会専門医
- 日本消化器内視鏡学会専門医
-
診療助教
浅田 翔平あさだ しょうへい
専攻分野 - 消化管・肝・胆・膵 疾患
所属学会 - 日本内科学会
- 日本消化器病学会
- 日本消化器内視鏡学会
- 日本肝臓学会
- 日本胆道学会
- 日本膵臓学会
主な資格・認定 - 日本内科学会認定内科医
- 日本消化器病学会専門医
- 日本肝臓学会専門医
- 日本消化器内視鏡学会専門医
コメント 胆膵疾患を中心に、外来で消化管癌、肝疾患、炎症性腸疾患等消化器疾患全領域を診療しています
-
助教 (中央内視鏡部)
岩井 聡始いわい さとし
専攻分野 - 消化管・肝・胆・膵 疾患
所属学会 - 日本内科学会
- 日本消化器病学会
- 日本消化器内視鏡学会
- 日本消化管学会
- 日本肝臓学会
主な資格・認定 - 日本内科学会認定医
- 日本消化器病学会専門医
- 日本消化器内視鏡学会専門医
- 日本肝臓学会専門医
コメント 患者様が安心して治療に臨めるよう、分かりやすい説明と安全確実な治療を目指します。
-
医員
小泉 有利こいずみ ありとし
専攻分野 - 消化管・肝・胆・膵 疾患
所属学会 - 日本内科学会
- 日本消化器病学会
- 日本肝臓学会
- 日本消化器内視鏡学会
主な資格・認定 - 日本内科学会認定内科医
- 日本消化器病学会専門医
- 日本肝臓学会専門医
- 日本消化器内視鏡学会専門医
-
診療助教
芝本 彰彦しばもと あきひこ
専攻分野 - 消化管・肝・胆・膵 疾患
所属学会 - 日本内科学会
- 日本消化器病学会
- 日本肝臓学会
- 日本消化器内視鏡学会
主な資格・認定 - 日本内科学会認定内科医
- 日本消化器病学会専門医
- 日本肝臓学会専門医
- 日本消化器内視鏡学会専門医
-
医員
田中 美彩子たなか みさこ
専攻分野 - 消化管・肝・胆・膵 疾患
所属学会 - 日本内科学会
- 日本消化器病学会
- 日本肝臓学会
- 日本消化器内視鏡学会
主な資格・認定 - 日本内科学会認定内科医
- 日本消化器病学会専門医
- 日本消化器内視鏡専門医
- 日本肝臓学会専門医
-
医員
松田 卓也まつだ たくや
専攻分野 - 消化管・肝・胆・膵 疾患
所属学会 - 日本内科学会
- 日本消化器病学会
- 日本肝臓学会
- 日本消化器内視鏡学会
主な資格・認定 - 日本内科学会認定内科医
- 日本肝臓学会専門医
-
医員
依岡 伸幸よりおか のぶゆき
専攻分野 - 消化管・肝・胆・膵 疾患
所属学会 - 日本内科学会
- 日本消化器病学会
- 日本肝臓学会
- 日本消化器内視鏡学会
主な資格・認定 - 日本内科学会認定内科医
- 日本消化器病学会専門医
- 日本肝臓学会専門医
- 日本がん治療認定機構がん治療認定医
-
医員
増田 泰之ますだ ひろゆき
専攻分野 - 消化管・肝・胆・膵 疾患
所属学会 - 日本内科学会
- 日本消化器病学会
- 日本肝臓学会
- 日本消化器内視鏡学会
主な資格・認定 - 日本内科学会認定内科医
-
医員
髙見 昌義たかみ まさよし
専攻分野 消化管・肝・胆・膵 疾患
所属学会 - 日本内科学会
- 日本消化器病学会
- 日本肝臓学会
- 日本消化器内視鏡学会
主な資格・認定 - 日本内科学会認定内科医
- 日本消化器病学会専門医
- 日本肝臓学会専門医
- 日本消化器内視鏡学会専門医
-
医員
花谷 純一はなたに じゅんいち
専攻分野 - 消化管・肝・胆・膵 疾患
所属学会 - 日本内科学会
- 日本消化器病学会
- 日本肝臓学会
- 日本消化器内視鏡学会
主な資格・認定 - 日本内科学会認定内科医
- 日本肝臓学会専門医
-
医員
中谷 達也なかたに たつや
専攻分野 - 消化管・肝・胆・膵 疾患
所属学会 - 日本内科学会
- 日本消化器病学会
- 日本肝臓学会
- 日本消化器内視鏡学会
主な資格・認定 - 日本内科学会認定内科医
- 日本消化器病学会専門医
- 日本肝臓学会専門医
- 日本消化器内視鏡学会専門医
-
医員
尾山 雅文おやま まさふみ
専攻分野 - 消化管・肝・胆・膵 疾患
所属学会 - 日本内科学会
- 日本消化器病学会
- 日本肝臓学会
- 日本消化器内視鏡学会
主な資格・認定 - 日本内科学会認定内科医
- 日本消化器病学会専門医
- 日本肝臓学会専門医
- 日本消化器内視鏡学会専門医
-
医員
西村 尚起にしむら なおき
専攻分野 - 消化管・肝・胆・膵 疾患
所属学会 - 日本内科学会
- 日本消化器病学会
- 日本肝臓学会
- 日本消化器内視鏡学会
-
医員
撫井 由香むい ゆか
専攻分野 - 消化管・肝・胆・膵 疾患
所属学会 - 日本内科学会
- 日本消化器病学会
- 日本肝臓学会
- 日本消化器内視鏡学会
-
大学院生
森 仁志もり ひとし
専攻分野 - 消化管
所属学会 - 日本内科学会
- 日本肝臓学会
- 日本消化器病学会
- 日本消化器内視鏡学会
- 日本消化管学会
- 日本胃癌学会
主な資格・認定 - 日本内科学会認定内科医
- 日本肝臓学会専門医
- 日本消化器病学会専門医
- 日本消化器内視鏡学会専門医
- 日本消化管学会胃腸科専門医
コメント 消化器疾患の中で特に消化管について研鑽を積んで参りました。患者様に寄り添った、診察・治療を心がけています。何でもご相談ください。
-
大学院生
岩田 臣弘いわとみ とみひろ
専攻分野 - 消化器疾患全般
所属学会 - 日本内科学会
- 日本消化器病学会
- 日本消化器内視鏡学会
- 日本肝臓学会
- 日本膵臓学会
- 日本胆道学会
主な資格・認定 - 日本内科学会認定内科医
コメント 奈良県の医療に貢献できるように頑張ります。
-
大学院生
元川 雄貴もとかわ ゆうき
専攻分野 - 消化器疾患全般
所属学会 - 日本内科学会
- 日本消化器病学会
- 日本消化器内視鏡学会
- 日本肝臓学会
- 日本胆道学会
- 日本膵臓学会
主な資格・認定 - 日本消化器病学会専門医
- 日本肝臓学会専門医
コメント 臨床、研究ともに全力で取り組みます。
-
大学院生
大﨑 結衣おおさき ゆい
専攻分野 - 消化器疾患全般
所属学会 - 日本内科学会
- 日本消化器病学会
- 日本消化器内視鏡学会
- 日本肝臓学会
- 日本胆道学会
- 日本膵臓学会
主な資格・認定 - 日本内科学会専門医
- 日本消化器病学会専門医
- 日本消化器内視鏡学会専門医
コメント 消化器疾患を中心に日々の診療および研究に励みたいと思います。よろしくお願いいたします。
-
大学院生
加知 宏規かち ひろき
専攻分野 - 消化器疾患全般
所属学会 - 日本内科学会
- 日本消化器病学会
- 日本消化器内視鏡学会
- 日本肝臓学会
- 日本門脈圧亢進症学会
主な資格・認定 - 日本内科学会専門医
- 日本消化器病学会専門医
- 日本消化器内視鏡学会専門医
-
専攻医
森本 拓馬もりもと たくま
専攻分野 - 消化器疾患全般
所属学会 - 日本内科学会
- 日本消化器病学会
- 日本肝臓学会
- 日本消化器内視鏡学会
コメント よろしくお願いします
-
専攻医
仲川 慎哉なかがわ しんや
専攻分野 - 消化器疾患全般
所属学会 - 日本内科学会
- 日本消化器病学会
- 日本肝臓学会
- 日本消化器内視鏡学会
-
専攻医
堀木 翔太ほりき しょうた
専攻分野 - 消化器疾患全般
所属学会 - 日本内科学会
- 日本消化器病学会
- 日本肝臓学会
- 日本消化器内視鏡学会
コメント よろしくお願いします。
-
専攻医
余田 智史よだ さとし
専攻分野 - 消化器疾患全般
所属学会 - 日本内科学会
- 日本消化器病学会
- 日本肝臓学会
- 日本消化器内視鏡学会
コメント よろしくお願いします。
-
専攻医
米田 健人よねだ けんと
専攻分野 - 消化器疾患全般
所属学会 - 日本内科学会
- 日本消化器病学会
- 日本肝臓学会
- 日本消化器内視鏡学会
コメント よき医療を目指して精進したい所存です。ご指導ご鞭撻をよろしくお願いいたします。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1診 |
波崎 (肝臓・生活習慣病) |
吉治 (肝臓・生活習慣) |
鍛冶 (肝臓・食道・胃) |
美登路 (食道・胃・胆膵) |
佐藤 (肝臓・消化管) |
|
| 2診 |
辻 (肝臓・消化管) |
北川 (食道・胃・胆膵) |
久保(消化管) |
西村典 (肝臓・消化管) |
藤永 (肝臓・食道・胃) |
|
| 3診 | 松田(消化管) | 岩井(消化管) |
浅田 (胆膵・消化管・肝臓) |
依岡 (消化管) |
小泉 (消化管) |
|
| 4診 |
花谷 |
★田中 (消化管) |
友岡 (食道・胃・胆膵) |
芝本 (肝臓・消化管) |
森 |
|
| 5診 | 中谷 | 高見 | 尾山 |
増田 (消化管) |
元川(初診) | |
| 6診 | 西村尚(初診) | 岩田(初診) | 加知(初診) | ★大崎(初診) | ||
※★は女性医師です。
直近の休診・代診情報
-
休診
-
休診
-
休診
-
- B型肝炎ウイルス陽性と言われました。特に症状もないのですが、治療は必要ですか?
- B型肝炎ウイルスが陽性であっても、症状が出ない患者様がほとんどです。まずは専門病院を受診して、詳しい検査を行い、血液中のB型肝炎ウイルスの量や、肝障害の程度によっては、ウイルス治療が必要と判断されることもあります。ウイルス治療が必要でなくても、B型肝炎に感染していると、肝臓がん発症のリスクがあるので、定期的な検査が望ましいです。
-
- C型肝炎ウイルス陽性と言われました。特に症状もないのですが、治療は必要ですか?
- B型肝炎と同じく、C型肝炎ウイルスが陽性であっても、症状が出ない患者様がほとんどです。一方で、B型肝炎と異なり、基本的にはC型肝炎ウイルスに感染している患者さんはほぼ全員が治療対象となります。最近は治療方法が進歩し、数カ月の内服治療で副作用も少なく、完全にC型肝炎ウイルスを排除できることができるようになっています。
-
- ピロリ菌を除菌したら、その後は胃カメラを受けなくてもいいですか?
- ピロリ菌は胃がん発生の最大の原因であり、ピロリ菌を除菌することで胃がん発生のリスクを下げることができます。しかし、胃がんが発生しなくなるわけではなく、除菌から5年、10年経過してから胃がんが発生することもあり、除菌後も定期的な胃カメラを受けて頂くのが望ましいです。









